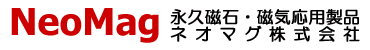【ネオジム磁石の着磁工程】
下図はネオジム磁石の製造工程です。今月はこの中の着磁工程についてのお話をします。その前工程として図示しました検査工程は、着磁前に実施する検査と着磁後に実施する検査がありますので、今月はまず、着磁工程について解説させていただき、検査工程については次回にお話をいたします。
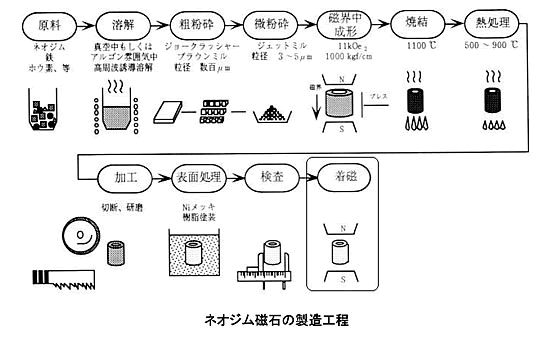
1.永久磁石の着磁について
「着磁とは磁性体に外部磁場を加えて磁化させること」ですが、着磁前の磁性体は右図(1)のように、磁気モーメント(自発磁化)が一定方向に揃っている複数の原子の集団があり、これが磁区です。磁区の境界は磁壁と呼びます。通常は磁区の方向はバラバラに向いていて、お互いに打ち消しあって外部に磁化が現れていません。この状態で外部磁場を加えると、各磁区の磁気モーメントの方向が外部磁場方向に揃い磁化が発生する、つまり着磁するというわけです。
これらの磁化過程をさらに磁化曲線との関連で詳細にみると、右図に示したように、初磁化曲線((1)~(5))に沿って磁場強度が上昇するにつれ、印加磁場方向への磁区の磁化反転が進行し、磁壁が移動してゆきます。最終的には磁場と同一方向に着磁時の磁化過程と磁壁移動回転磁化が起こって飽和に至ります。
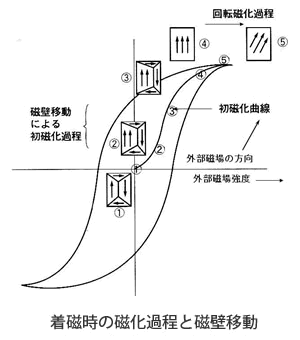
2.ネオジム磁石の着磁方法
着磁法には静磁場によって行う方法と、パルス磁場による方法があります。下図にこれらの着磁法を示しました。飽和に近い着磁状態を得るには、自発保磁力(Hcj)の少なくとも1.5倍程度の着磁磁場強度が必要といわれていますが、ネオジム磁石の場合はHcjの大きさに関係なく、1600[kA/m](20kOe)以上の磁場があれば十分です。
静磁場による着磁法は、大きな磁石を着磁する場合に用いられ、通常は電磁石が使われます。パルス磁場による着磁法では短時間で着磁できますので、着磁サイクルを上げられ生産性が高く、量産工程向きです。特に図のような多極着磁はパルス磁場のみで可能です。パルス磁場は、コンデンサバンクに蓄えた電荷を空芯コイルを設置した磁気回路に瞬時に放電させることにより、そのコイルに瞬間大電流をを流して発生させます。
パルス着磁の場合、被着磁磁石体に渦電流が誘起され磁場の浸透が妨げられて、着磁が不十分な場合があります。これを避けるために、永久磁石の着磁方法なるべく回路の時定数を大きくして、パルス幅を大きくする必要があり、数ミリ秒幅の比較的長いパルスが望ましいとされています。必要とされるコンデンサの蓄積エネルギーはコイル径、したがって被着磁磁石の直径の2乗で増加します。このため、大型磁石を着磁するためには大容量のコンデンサー電源を有するパルス着磁装置もしくは強磁場が可能な電磁石が必要となります。電磁石による磁場(直流磁場)で飽和まで着磁する場合は、フェライト磁石で15kOe(1200kA/m)、ネオジム磁石で20kOe(1600kA/m)程度の磁場が必要です。また、コンデンサー着磁器によるパルス着磁では着磁コイルの設計にもよりますが、以下の電源条件が一般的です。
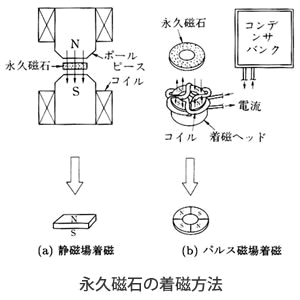
電源のパワー(エネルギー)は、E=(1/2)CV2[J]となり、電圧(V)とコンデンサーの静電容量(F)に関係します。実用的な電圧、コンデンサー容量は、フェライト磁石では、1000(V)、1000(μF)以上、ネオジム磁石では1500(V)、2000(μF)以上が必要とされているようです。下の写真は実際のパルス着磁装置のコンデンサ・パルス電源と着磁コイルの一例です。


3.ネオジム磁石の着磁(方向、極数)の種類
下図にネオジム磁石(NeoMag)の主要な着磁の種類を示しました。メーカーにより着磁の呼称が若干異なる場合がありますのでご注意ください。なお、多極着磁の場合は空芯コイルを使えないため、磁石仕様に合わせた特殊な着磁コイルが必要になります。但し、着磁電流をあまり減らすことができないために着磁コイルの線径を細くする限度があり、極端な多極着磁はできません。このような超多極や複雑な着磁の場合は、着磁電流が少なく済む等方性のネオジムボンド磁石やネオジムラバー磁石を使うことがあります。
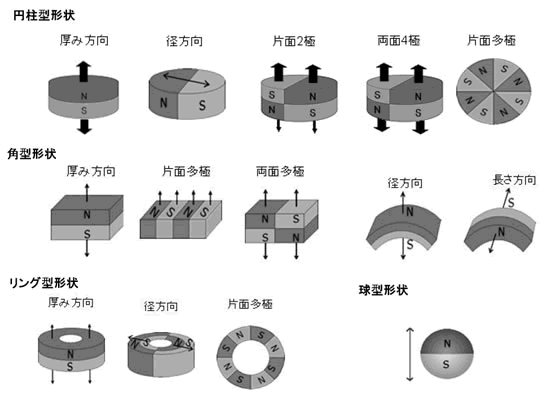
以上、ネオジム磁石の着磁工程についての解説をいたしましたが、永久磁石は形になったらすぐに磁力を持つようになるわけではなく、外から磁場(磁界)を与えて原子や分子の持つ磁気の力(磁気モーメント)を同じ方向に揃えて、初めてその磁力が外部に発揮できることがお分かりいただけたと思います。
次回は製造工程図とは順序が前後しますが、ネオジム磁石の測定・検査工程についてお話をする予定です。
(参考資料)
「永久磁石・材料科学と応用」佐川眞人・浜野正昭・平林 眞(アグネ技術センター)
「希土類永久磁石」俵 好夫・大橋 健 (森北出版)
「NeoMagホームページ、カタログ」