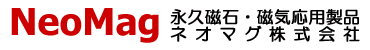いよいよ今月は再生可能エネルギーについての最終回です。過去8回にわたり種々の再生可能エネルギーについて勉強してきましたが、今月はそれら各種再生可能エネルギーの将来性を“エネルギー効率”、“実用コスト”、“技術的な将来性”などの観点から比較してみたいと思います。
(6-11) 再生可能エネルギーの比較
[1]指標-1:エネルギー資源の集中度(密度)
さまざまな再生可能エネルギーを比較するにあたって、わかりやすい発電について比較してみたいと思います。なお、バイオマスエネルギーについては、燃料への利用もありますが、ここでは発電に限って比較することとします。
まず、考慮すべき指標から考えてみましょう。発電するといいますが、エネルギーは全体として増えも減りもしないのですから、なにか元になるエネルギーがあって、それを電気エネルギーに変換することを発電するということになります。そもそも、再生可能エネルギーに付けられている名称は、変換前のエネルギーに関係した現象を表しています。風力発電は風力、地熱発電は地熱といった具合です。風力は風の運動エネルギー、地熱は熱エネルギーですね。もっと大元をたどれば、地熱発電は地球内部での放射性物質の持つ核エネルギーになります。それ以外は全て太陽光エネルギーを元にしていますが、太陽光もそもそもの大元といえば、太陽の核融合エネルギーといえます。
われわれにとっては、ある発電設備から一定の期間内、たとえば一年間に取り出せる電気エネルギーの量(年間発電量)が大切です。取り出せる電気エネルギー量は、設備が取りこむことのできる、電気エネルギーに変換する前のエネルギー量に比例します。取り込むことのできる、変換する前のエネルギー量は、そのエネルギーの集中度と取り込む発電装置の大きさで決まります。つまり、変換前のエネルギーの集中度が考慮すべき指標の1つになるでしょう。エネルギーの集中度という観点では、集中しているのは、地熱発電と波力発電でしょう。地熱はそもそもまとまって存在しており、実は波力はエネルギー密度が高いのです。
また、小水力発電は河川に限られ、ある程度集中していると考えてよいでしょう。太陽光や風力は、もちろんエネルギー量としては膨大に存在するのですが、エネルギー密度としては低いのです。
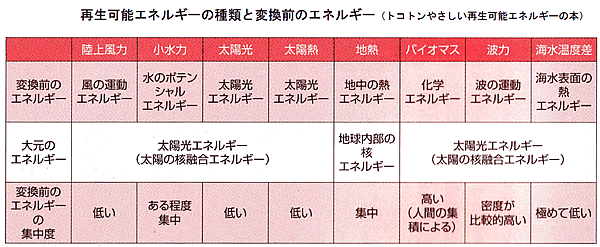
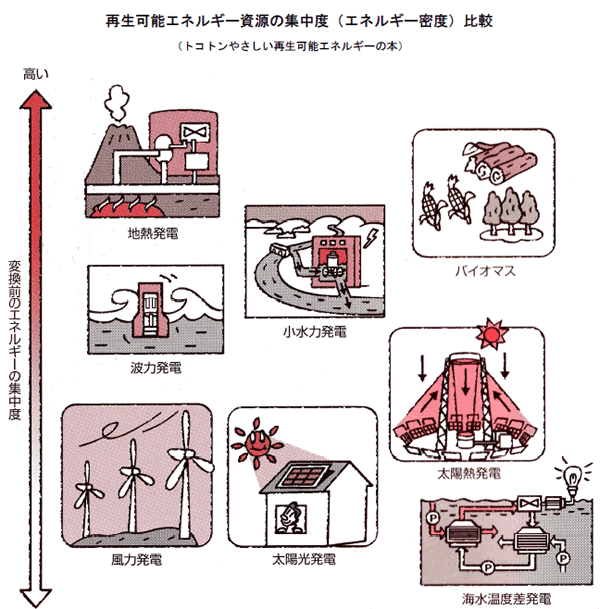
[2]指標-2:電気エネルギーへの変換効率
取り込んだエネルギーのうち、どれだけを電気エネルギーに変えることができるかがエネルギー変換効率です。ある設備の発電能力、すなわち設備容量は変換効率に比例します。エネルギー変換効率は、もっとも小さなのが海洋温度差発電の1~3%、10%以上程度が太陽光発電、地熱発電、陸上風力発電、波力発電で、太陽熱は40%といわれており、最高値は小水力発電の80%です。これらは、理論的に上限が定まっており、それにいかに近づけるかが技術開発の目標です。
次にどの程度安定に発電できるかも重要な指標です。従来の火力発電や大規模水力発電などは、あらかじめ用意してある燃料や貯水を制御して、需要にあわせて発電することができました。再生可能エネルギーの中で、もっとも安定に発電できるものは、海水温度差発電と地熱発電、それにバイオマス発電でしょう。海水の温度差はそう簡単には変わらないし、地熱も地球内部の熱なのでそうそう変化しません。
次に安定なのは小水力でしょう。河川の水も、大方は安定に流れているものです。バイオマスも、あらかじめ人間が燃料を用意しておくので、安定に発電できます。波、風、太陽光は天候の影響を大きく受けるため、どうしても不安定にならざるを得ません。それを数値で表すと設備利用率になります。設備利用率は海水温度差発電は80~90%、続いて地熱発電が80%、小水力が60%、バイオマスが40~60%と続きますが、あとは下がって、波力発電が30%程度と推定されており、陸上風力発電が20%、太陽光発電が12%になっています。これは設備容量と発電量の違いになって現れてきます。
実際の発電量は、設備容量に設備利用率を乗じたものになります。太陽光や風力の設備容量は大きいのですが、設備利用率が低いために発電量は大きくはありません。
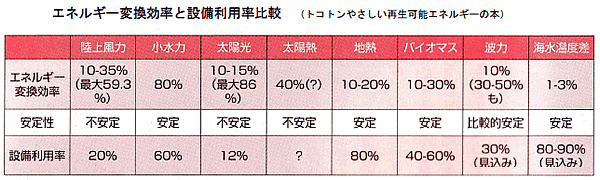
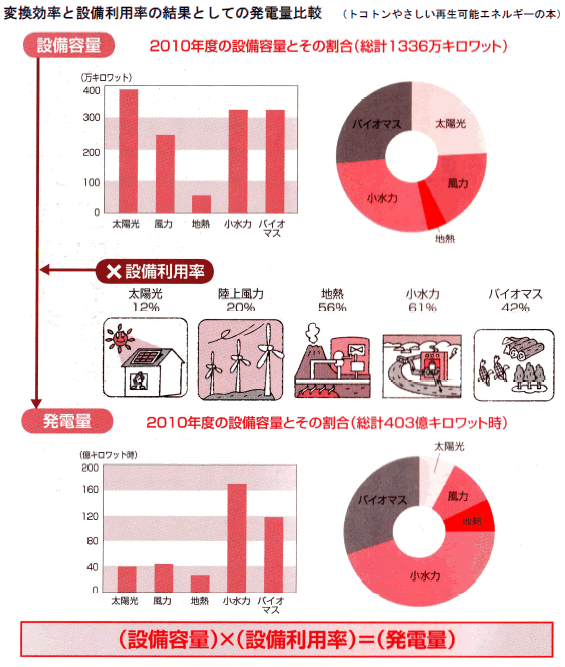
[3]指標-3:再生可能エネルギー発電設備のコスト比較
設備は使っているうちに老朽化します。発電設備が期待された能力を発揮できる期間を稼動年数といいます。期待値も入っていますが、風力や太陽光では20年、小水力、地熱、バイオマスでは40年程度が見積もられています。
そして、コストです。発電コストにはさまざまな要因が含まれます。まず目的とする発電能力、すなわち目的とする設備容量をもつ設備の建設費が含まれます。ここには、物理的要因として電気に変換する前のエネルギーの集中度や密度、およびエネルギー変換効率がきいてきます。電気に変換する前のエネルギーが集中しており密度が高く、さらにエネルギー変換効率が高い方がコストは安くなります。当然、設備利用率が高い方が無駄なく装置が動いていることになりますし、稼動年数も長く使えた方がコストは下がります。現状では、地熱や風力、小水力が比較的安価であり、バイオマスが続き、太陽光が少し高くなっています。波力と海洋温度差についてはまだまだ高価と予想されます。ただし、このコストは革新的な技術が開発されると一気に下がる可能性があります。
石炭・天然ガス・石油を燃料とした火力発電のコストはキロワット時あたりそれぞれ、5~7円、6~7円、14V17円ですから、よりコスト低減が望まれます。ほかの評価指標としてエネルギー収支比(EPR)やエネルギーペイバックダイム(EPT)がありました。EPRでは、風力と小水力が、設備をつくるために必要としたエネルギーの50倍に達する電気エネルギーを変換してくれることがわかります。次いで地熱と太陽光が続きます。バイオマスのEPRはあまり大きくありません。波力や海水温度差はまだ技術が未開発で小さなEPRにとどまっています。EPRも技術開発が進み、大量生産できるとさらに大きくなります。
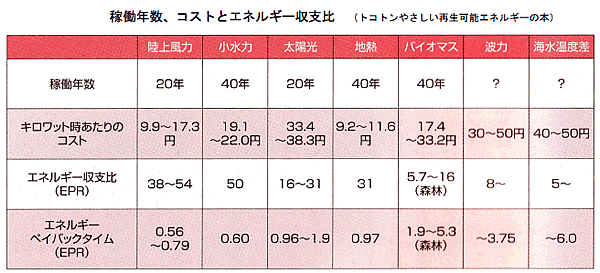
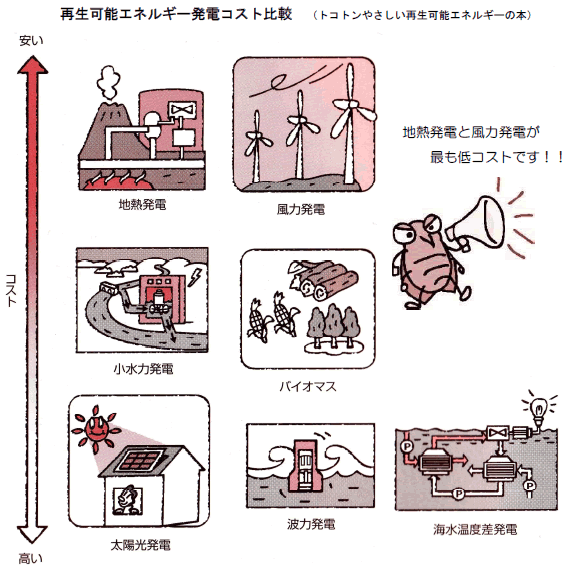
[4]日本の再生可能エネルギーの将来性
再生可能エネルギーで開発可能なエネルギー量を導入ポテンシャルと呼びます。日本国内における導入ポテンシャルはいずれもかなり大きいものと試算されています。どこまで期待してよいのでしょうか。われわれは、どこまでが物理的な制約で、どれが技術的な事実で、どれが仮定なのかを理解して、その結果を現実的に評価することが必要です。
たとえば、太陽光発電を例にとってみると、日本では1平方メートルあたり年間1400キロワット時の太陽光エネルギーを受け取っていることは物理的事実です。そして太陽電池のエネルギー変換効率が10%として、太陽電池1キロワットあたりの年間発電量は約1000キロワット時となります。2009年の総発電量9511億キロワット時の10%を太陽光発電でまかなうためには680平方キロメートルが必要と計算できます。効率の10%は現状の値で、総発電量の10%をまかなうというのは計算の仮定です。
住宅太陽光発電の平均設備容量が4キロワットなので、太陽電池を載せた住宅1戸あたり1年間で約4000キロワット時の発電量になります。総発電量9511億キロワット時の10%をまかなうには、約2400万戸、おおよそ日本の住宅の半分に載せることが必要です。日本では2012年4月末までの国内における住宅用太陽光発電システムの累計設置件数が、100万件に達しました。その24倍の量を載せることが必要です。10年で達成するとして1年間に240万戸必要です。2010年は年間約20万戸弱でした。費用もかかります。経済的側面や政策的な面も考慮して評価しなければなりません。
ほかの再生可能エネルギーも同じ状況にあります。われわれには、何を目的として、どの程度の効果を期待して導入するのかということ差総合的に判断することが求められているのです。
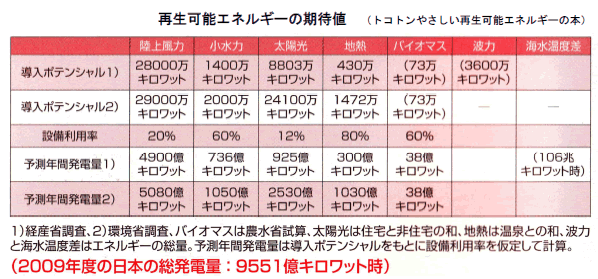
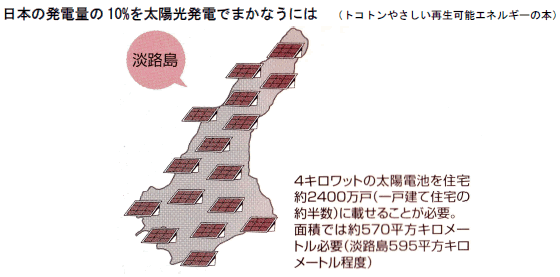
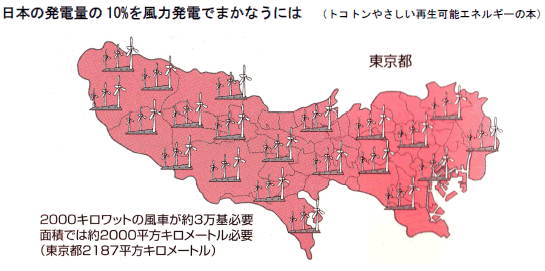
以上で再生可能エネルギーについては終了です。世界中の人々の再生可能エネルギーへの期待と夢は大きいのですが、現実問題として再生可能エネルギーを現在の基幹エネルギーへの代替とするにはまだまだ時間が必要なことがわかりました。しかしながら、着実にその利用を拡げてゆくことと、官民一体となった将来へ向けての技術開発をしてゆくことにより、いつか再生可能エネルギーを人類の基幹エネルギーに位置づけることができる日がやってくるのではないでしょうか。
<参考・引用資料>
「トコトンやさしい再生可能エネルギーの本」太田健一郎 監修、石原顕光 著 日刊工業新聞社
「新エネルギー・産業技術開発機構(NEDO)」 ホームページ